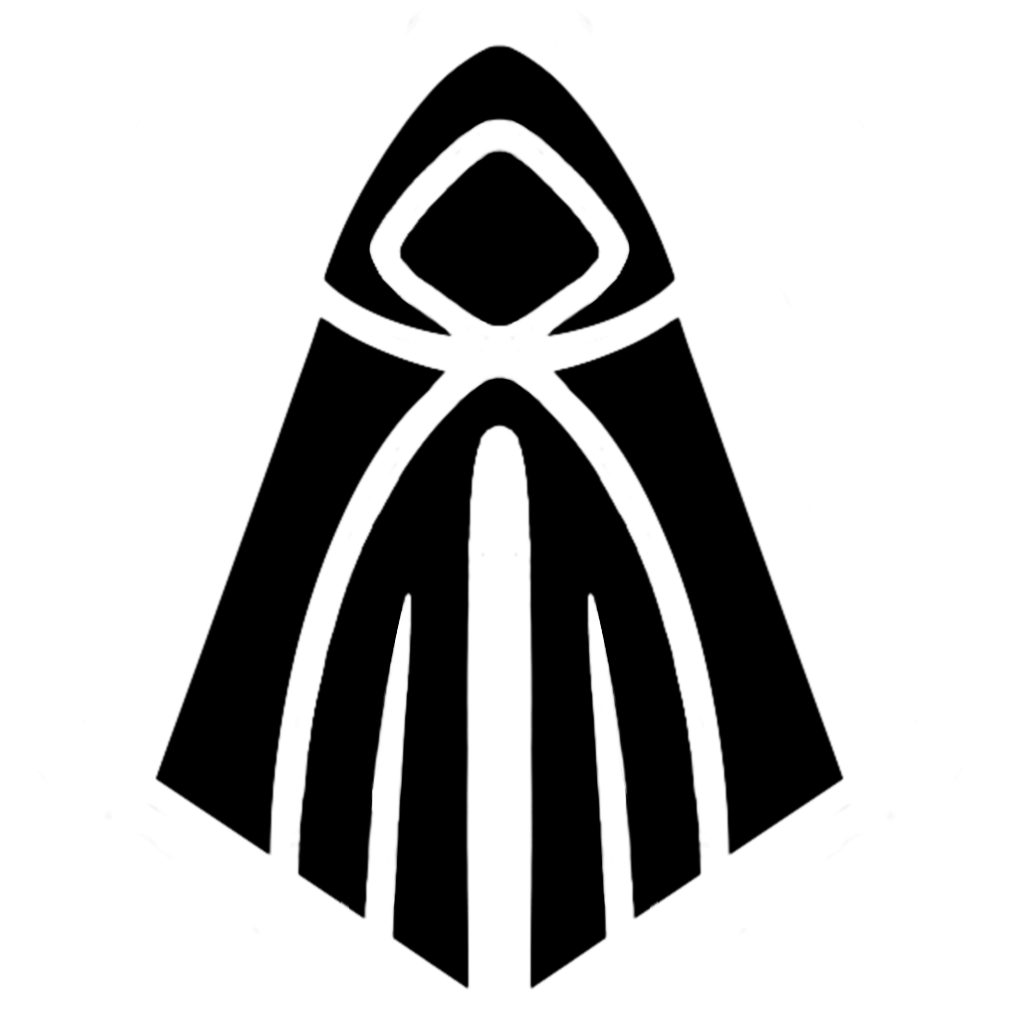夢は、檻だ。
おれは毎夜、その鉄格子に閉じ込められ、逃げ場のない同じ悪夢を繰り返し見ていた。
橙の光が続く夜の山道。
迫ってくる黒い異形。
血に染まり、崩れ落ちる家族と友。
おれがすぐ動かなかったから。
おれが無茶をしたから。
後悔の言葉を何度口にしても、悲しみに沈んでも、過去は戻らない。
八日前のあの日の再現。
おれはその底なしの闇を、何度も何度もさまよった。
――けれど、今夜は違った。
いつもの檻に現れたのは、街で見かけた、鳥にも似た黒い生き物だった。
音もなく浮かび、目は赤黒く染まっている。
ネットでいくら探しても正体のつかめなかった、あの得体の知れない存在。
そして、どこからともなく、沈んだ緑の目をした男が現れた。
視線は冷え切っていて、こちらを射抜きながら一歩ずつ近づいてくる。
ぴったりしたシャツに、脚にはポーチを着けている。
特殊な訓練を受けたであろう軍人を連想させた。
いつもの夢には決していなかった二つの異物。
その侵入によって、おれの悪夢は“本物の悪夢”へと姿を変えた。
痛みが全身を駆け抜ける。
鈍さと鋭さが入り交じり、現実の感覚をそのまま押しつけられたような苦痛。
腕。背中。脇腹。鳩尾。
食らうたび、頭が揺れ、視界が白くはじけ飛ぶ。
夢の中なのに、意識が遠のいていくような気さえする。
世界がぐるぐる回り、自分がどこにいるのかもわからなくなる。
状況を理解する余裕も、息を整える間もない。
ただ必死に、檻の中を駆け回った。
ようやく夢から覚めたとき、おれは自分の部屋の真ん中に突っ立っていた。
逃げられた――
張り詰めていた神経が緩み、息を一気に吐いた。
やっぱり夢だった。
夢でよかった……本当に。
そう心の中でつぶやいて、窓の外に目をやる。
遠くの山の麓を、霧が静かに這い上がっていく。
その上に丸い月が浮かんでいる。
だが、今夜の月は、どこか色を失ったように、灰をかぶった円盤のように見えた。
もうしばらくすれば、夜も明けそうだ。
夢の中で痛めつけられた脇腹に手を当てた。
痛みは、ない。
けれど、すぐ別の異変に気づき、おれは眉をひそめた。
服や肌に触れているはずなのに、指に確かな質感が伝わってこない。
いや、触れていることはわかる。
わかるのに、指先から伝わるものがやけに鈍い。
麻酔が効きはじめたときの、あのじわじわした曖昧さに近い。
薄い膜を一枚挟み、その上から撫でているかのようだ。
手元を見下ろして、おれは目を見開いた。
手が――透けている。
透けた先には、床板の木目までくっきりと見えていた。
頭が追い付かない。
鼓動が耳の奥でやかましく反響し、呼吸のリズムを乱していく。
恐る恐る、視線を腕へ。
そこから胴へと、なぞるように落としていく。
手だけじゃない。
腕も、肩も、胸も、足も――全身が透けている。
冷えた夜気も肌に触れているはずなのに、その存在ごと奪われたように何も伝わってこない。
まだ夢を見ているのか?
おれは頬をつねった。
痛みは……ある。
だが鈍い。
落ち着け。
深呼吸だ。
ひとつずつ確認しろ、今起きていることを。
振り返って、寝ていたはずのベッドを見る。
その瞬間、おれは凍りついた。
そこには――おれの身体が、まだ眠っていた。
そして、抜け殻のはずの身体が、ゆっくりとまぶたを持ち上げた――
夢の檻は、壊された。
夢も現実も、おれの知っている世界から外れはじめる。
すべてが狂い始めたのは、八日前――“昏渡り”の日からだ。