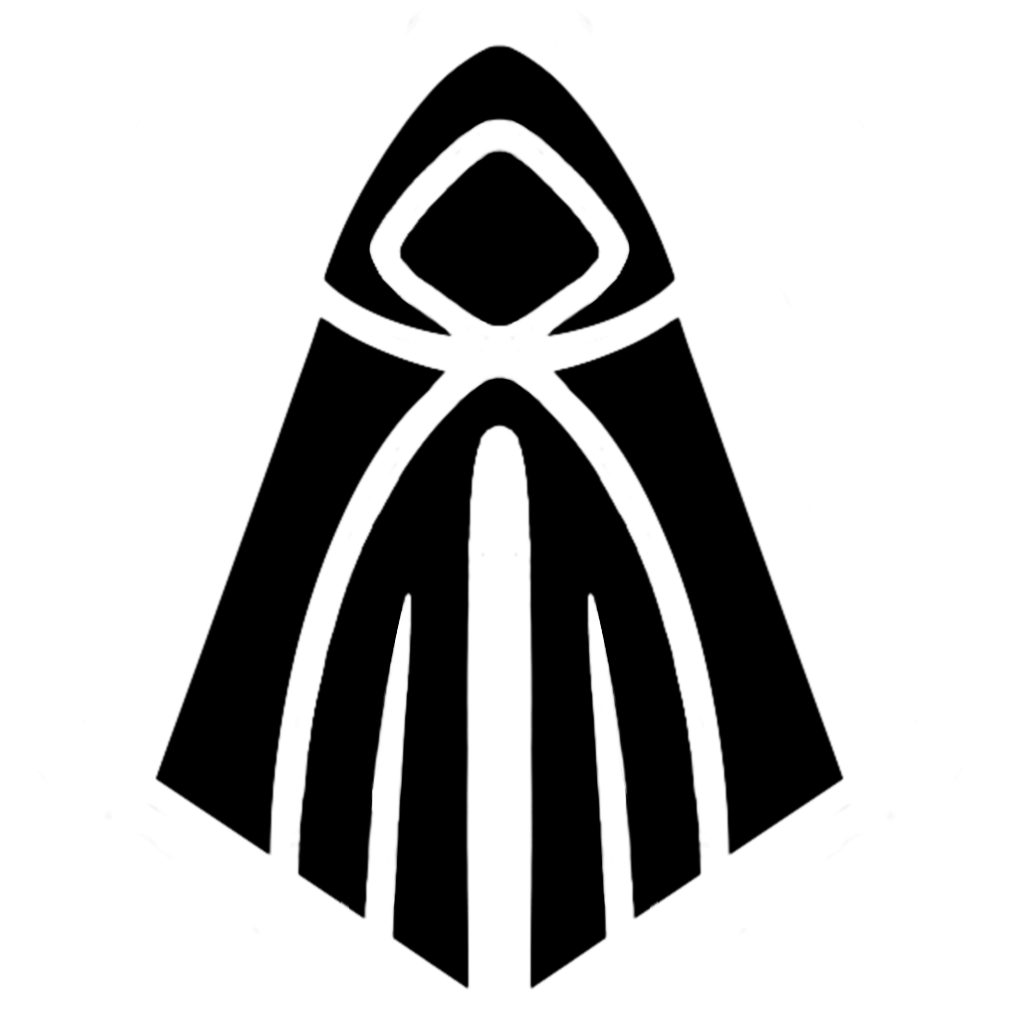夢は、檻だ。
サニは毎晩、同じ悪夢をさまよっていた。
夜の山道。
逃げ惑う人々。
人の形をした、黒い影。
そして――
サニを守ろうとして、血に染まる家族と友人。
だが、今夜は違った。
夢の檻が、壊された。
目を覚ましたサニのベッドに、自分と瓜二つの“誰か”が眠っていた。
夢の中に現れた、見知らぬ男。
その出会いを境に、夢も現実も、サニの手を離れていった。
すべてが狂い始めたのは八日前。
“昏渡り”からだった。
***
頭から足首まで白一色。
ゆったりとした儀式用のローブに身を包み、サニは腰で細い紐を結んだ。
こんな格好をする機会なんて、今どきめったにない。
「このローブ着てると、気温ちょうどいいな」
生地を軽くなでながらつぶやくと、隣のスノアが襟元をぱたぱたあおいだ。
「俺はちょっと暑いくらいだ」
前を見ると、レイルは背伸びして人垣の向こうをのぞこうとひょこひょこと動き、クラウトは無表情で空を見上げている。
夕方なのに空は澄み渡った青。
夏だというのに、ほんの少し肌寒かった。
ここ、エズミアの市街広場では、まもなく“昏渡り”の儀式が始まる。
広場の中央には、山のように積まれた薪。
それを正面に、左右二つの大きな集団――白いローブをまとった何百人もの子どもたちが並んでいる。
サニたちは右側の列にいた。
白ローブの集団をぐるりと囲むロープの外側には、地元の人や観光客が大勢いる。
みんな今か今かと儀式の開始を待っている。
半袖で腕をさすっている観光客の姿もちらほらあった。
エズミアの夏を知らずに来たのだろう。
思ったより冷える空気に驚いているに違いない。
サニは、ローブの紐をきつく結び直した。
昏渡り――それはエズミアに古くから伝わる成人の儀式。
年に一度、十五歳を迎えた子どもたちが、大人として認められるための通過儀礼だ。
今年、サニも十五歳になった。
同い年の友人、スノア、レイル、クラウトと共に参加する。
そのため、今こうして、白い儀式用ローブに身を包み、市街広場に立っている。
儀式は、広場中央に積まれた薪に火が灯される開会式から始まる。
炎をキャンドルに移し、それをランタンに入れて街中や山道を歩く。
行進が終わると、山上で行われる誓いの儀式が待っている。
この日、若者たちは街の前でお披露目される。
エズミアの人々にとって、それは次の世代を見届ける大切な節目だ。
通りを彩る装飾も、新成人へ向けられる声援も、その思いの深さを物語っていた。
ざわめく広場に、澄んだ鈴の音が高く響いた。
群衆の声がぴたりと止む。
静寂が波のように広がり、人々の視線が一斉に広場奥の建物へ向かう。
白地に金の刺繍をあしらった祭服をまとった一団が姿を現した。
――昏渡りの開会式が、いよいよ始まる。
観衆の視線が集まり、カメラやスマホが次々と掲げられる。
最前列の報道陣が、盛大なフラッシュを浴びせていた。
「よく見えねーな」
レイルが列から体を乗り出し、サニの目の前で顔を左右に振る。
そのたびに視界が遮られる。
サニは苛立ち混じりにレイルの頭を両手でわしづかんだ。
「あんま動くなよ。邪魔だっての」
「見えねーんだから、しょうがねーだろ」
レイルの頭が揺れるたび、サニも視線をずらす羽目になる。
そこへ、スノアが二人の肩を小突いた。
「おまえら、毎年見てんだから、今年くらいおとなしく立ってろ。恥ずかしいだろが」
その言葉にクラウトが無言でうなずく。
レイルは不満げに口をへの字に曲げ、スノアをじろりとにらんだ。
それでも、渋々動きを止める。
ようやく、サニの視界が開けた。
正面――薪を高く積み上げた壇の前に、祭服の一団が並ぶ。
その中のひとりが火打石を高く掲げ、宙でカチリと打ち鳴らした。
小さな火花が、斜めに差し込む陽の光の中で散る。
そこへ、草束を抱えた男が歩み寄る。
火打石が何度か打ちつけられ、草束の先にぱちぱちと小さな炎が灯った。
焦げた香草の香りが漂う。
ほのかな苦みが鼻を抜け、夕方の空気に溶けていく。
サニは袖口で鼻を覆った。
この匂いだけは、どうにも好きになれない。
頭の奥がじんわりとくらむ。
やがて、一団の中心にいた代表者らしき男が前へ出る。
火のついた草束を受け取り、壇の上で深く頭を下げ――その炎を薪の中心へ投じた。
ごう、と音を立てて火が走った。
炎は瞬く間に駆け上がり、青空の下へ白い煙の筋を引く。
熱気が頬をなでた。
広場に歓声が湧く。
拍手と口笛が重なり、街全体がこの瞬間を祝っているかのようだ。
サニの胸も高鳴った。
形式だけの通過儀礼だとわかっていても、歓声に包まれているうちに、不思議と大人の一員になったような誇らしさが込み上げてくる。
祭服の者たちがキャンドルへ火を移し、それをランタンへ入れていく。
光がひとつ、またひとつと連なり、新成人たちの手へ渡っていった。
再び、澄んだ鈴の音が鳴り響く。
それを合図に、一団が列を組み、広場の中央を割るように歩き出した。
火を灯したランタンを手に、新成人たちもそのあとに続く。
「こっから“黒紫塔”まで、二時間以上も歩くのか……」
スノアが肩を落とし、ため息まじりにぼやく。
「誰が一番に山のふもとに着くか競争でもするか?」
レイルが両手をぶんぶん振り、冗談半分に駆け出す真似をしてみせた。
祭服と白ローブの列が向かう先には、広場からまっすぐ延びる大通り。
その先に、ゆるやかな山並が青空を切り取っている。
さらに奥――
空を突き抜けるようにそびえる、巨大な四角柱の構造物。
“黒紫塔”。
街全体を見下ろすように、静かに立っていた。
光を吸い込み、夜そのものを閉じ込めたかのような、謎めいた遺物。
サニにとって、それは儀式の終着点以上の存在だった。
幼いころ、母に手を引かれて見上げた日の空気が、今も鮮明によみがえる。
あの時から――あの塔は、ずっと特別なままだ。
火の灯ったランタンが、ひとつ、またひとつと、列に沿って手渡されていく。
温かな光が、夕方の大通りをゆっくりと流れる。
***
ランタンの火が、石畳の上でゆらゆらと揺れる。
日差しの中でも、その炎は鮮やかで、どこか現実離れして見える。
子どものころ、家族と見物したときも同じように感じたことを思い出す。
キャンドルから漂う、ほのかな甘い蝋の香り。
鼻先にふわりと届き、思わず深く息を吸い込んだ。
この匂いは、昔からわりと好きだ。
先頭からは、一定の間隔で澄んだ鈴の音が響く。
人々のざわめきの中でも、その音はくっきりと耳に届いた。
通りの両脇には、びっしりと人が並んでいる。
手を振る地元の人々、スマホを構えてシャッターを切る観光客。
道沿いのカフェやレストランは、今日のために色鮮やかに飾られていた。
テラス席では、酔った大人たちが笑い声を上げ、こちらにはほとんど注意を払わない。
街全体が、祭りの空気に包まれていた。
「昔の人って、こういうの好きだよな」
サニは手にしたランタンを、目の前で軽く揺らした。
隣を歩くスノアが、顔だけこちらに向ける。
「何の話だ?」
「こういう儀式だよ。意味があるんだかないんだか、よくわからないのに、続けるやつ」
クラウトも視線を向けてきたが、表情は変わらない。
その横から、レイルが顔を突き出す。
「最初にやり出したやつって、なんか面白そうって思ったくらいのノリだったんじゃね?」
サニは火を見つめながら、ふっと口元をゆるめた。
「ノリねー。ま、ありそうだな」
レイルの唇に、笑みが浮かぶ。
「だろ? 伝統って言えば聞こえはいいけど、結局は騒ぐ口実に始めただけとかさ」
「それがいつの間にか『由緒ある行事』になって、誰もやめられなくなる、みたいな?」
「そ。で、その誰かの思いつきに、今も俺たちは付き合わされてるってわけ」
レイルが肩をすくめ、手をぶらぶらと振って見せる。
「……でもさ」
クラウトが前を向いたまま口を開く。
「みんなが楽しそうなら、それでいいんじゃないか?」
それを聞いたレイルが凛々しい顔を作り、胸を張った。
「おい、俺はあんま楽しくもないぞ。こんな長々歩かされるくらいなら、この前買ったゲームの続きをしてるほうが楽しい」
サニは白い目をレイルに向けた。
「毎年見に来てて、さっきの開会式でもやけに前のめりだったくせに?」
「見るのとやるのは別だろ」
「なんでも楽しむほうが得だぞ」
「はいはい」
レイルは視線を逸らし、おどけた表情をすると、足元の石畳を軽く蹴った。
「……昔さ、じいさんから昏渡りの変な言い伝えを聞いたことがあって」
しばらく黙っていたスノアが、口を開いた。
サニは首をかしげる。
「変わった言い伝え?」
「どんな話だよ?」
レイルが大きくあくびをする。
スノアはこめかみを指で押さえながら続けた。
「じいさん曰く、昏渡りってのは、もともと“特別な魂”を別の世界へ送り出す儀式だったらしい」
やけに真面目な顔で何を話すかと思ったら、予想外の話だった。
サニは思わず笑いかけた。
「そんな話あるわけないだろ。ま、それが本当なら面白そうだけどな」
「……からかわれたんじゃないのか?」
クラウトが目を細める。
「いや、そういう感じじゃなかった。冗談なんてめったに言わないし、根拠のない話を信じる人でもなかった。その時も、本気の顔だった」
スノアの顔も真剣だ。
サニはなんとも言えない気持ちでクラウトと視線を交わす。
「じいさんの話だと、この世界とそっくりな“もうひとつの世界”があるらしい。
そこには、この世界に災いをもたらす存在がいる。
で、大昔――そいつらを遠ざけられる魂を送り出すために儀式を行っていた。それが形だけ残って、今の昏渡りになった、って」
レイルが口元を押さえ、吹き出すのをこらえている。
サニもつられて笑いかけた。
しかし、視線の先に黒紫塔が入った瞬間、その笑いは喉の奥で消えた。
スノアの話は、荒唐無稽に聞こえる。
けれど、その奥には――この世界には説明のつかない何かがある、と信じる揺るぎない思いがあった。
証明もできず、笑われるかもしれないものにさえ、スノアは意味を見いだしている。
その信じ方が、サニにはどこか自分と重なって見えた。
そして、不意に亡き母の姿を思い出させた。
母もまた、生涯をかけて黒紫塔の謎を追い続けた人だった。
必ず意味があると信じ、調べることをやめなかった。
今、その意志を継いでいるのはサニだ。
母が見つけられなかった答えを、自分の手で見つけ出す――それが、サニの目的になっている。
だから、レイルや他の人がスノアの話を笑うのは仕方がなくても、自分まで笑うわけにはいかなかった。
スノアは、自分と同じ側の人間だ。
証明のないものにも意味を見いだし、信じ続けられる人間。
スノアを笑うことは、母や自分が大切にしてきたものを否定するのと同じように感じた。
サニはそっと拳を握った。
スノアは視線を前に向けたまま、話を続けた。
「それと……塔の下に着いたら、何人か選ばれて首に油を塗られるだろ?
あれ、本当は“特別な魂”を無事にもうひとつの世界へ送り出すためのまじないなんだってさ」
その瞬間、レイルがこらえきれずに吹き出した。
「そんな話、マジで信じてんのか? スノアって意外とそういう話に弱いよな」
茶化す声に、スノアの頬がわずかに引きつる。
「……別に信じてるとは言ってない。ただ、そういう話を聞いたってだけだ」
「いやいや、そこまで細かく覚えてる時点で、ちょっとは信じてんだろ。
もしスノアが山ん中の儀式で選ばれたら、俺が拍手して異世界に送り出してやるから安心しろよ」
レイルはスノアの肩に手を置くと、満面の笑みでもう片方の手の親指を立てた。
スノアは何かを言い返しかけ、やめた。
短く息をつき、視線を逸らす。
いつものように、反論するだけ無駄だと判断したのだろう。
サニは無言で、スノアの横顔をちらりと見た。
そして、視線を遠くへ向ける。
空に突き刺さるようにそびえる黒紫塔。
スノアの聞いた言い伝えは、塔とも何か関係があるのかもしれない――
そんな考えが頭をよぎる。
もっと詳しく聞きたくて、胸の奥がそわそわと落ち着かなくなる。
けれど今ここで掘り返せば、きっとレイルが茶化してくるだろう。
また今度、ゆっくり聞けばいい。
いつだって聞けるはずだ――
そう、あの時は思っていた。
けれど、その”今度”が、ひっそりと遠ざかっていることに、この時はまだ気づいていなかった。