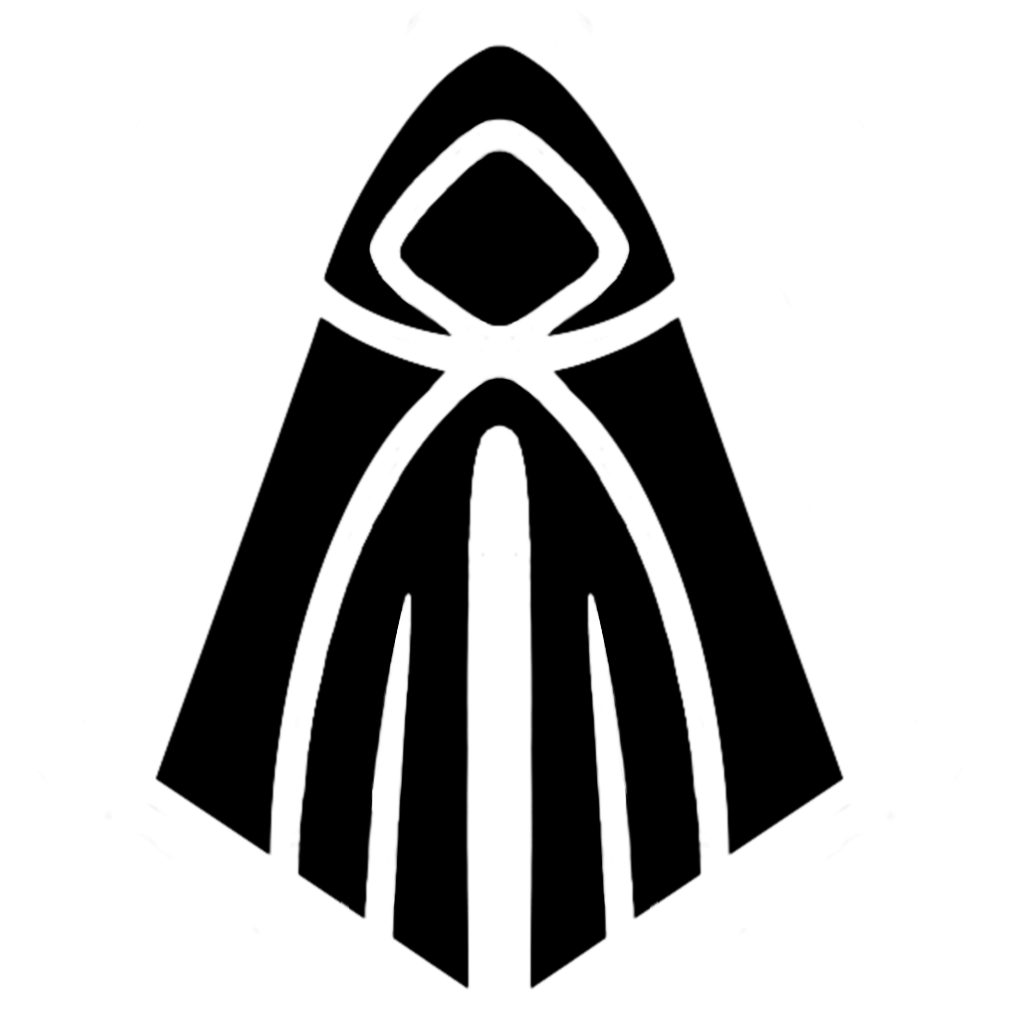緑に包まれた山道――
六歳のサニは、母に手を引かれて歩いていた。
しばらく歩くと、木立の切れ間から、黒紫塔が姿を現す。
黒紫塔は、ただそこにあるだけ。
目の前の初めて見る巨大な物体に、幼いサニは威圧され、息を呑んだ。
黒紫塔を調べる学者だった母は、夢中でペンを手帳の上に走らせる。
塔の表面を叩いて音を確かめる。
何かの機械を当て、画面を眺めてはまた書き記す。
観光客が物珍しそうに母のことを眺めていた。
一方、サニは、虫を追いかけたり、木に登ったりして、ひとり遊びはじめる。
母の仕事を見てみたいと、自分から無理についてきたにも関わらずだ。
時折、母の注意する声が飛んでくる。
やがて、遊ぶのにも飽きて、草むらに座りながら母をそばでじっと眺める。
眺めている間も、母は黙々と黒紫塔を調べている。
「なんでお母さんはこの壁、ずっと見てるの?」
幼いサニは、ただの黒い壁のようにしか見えない黒紫塔を指さす。
黒紫塔に向かって何時間も過ごす母が不思議でならなかった。
母はサニに向かってやわらかく微笑み、口を開いた――
***
山のふもとに着く。
サニは係員にランタンを預けた。
時刻は、すでに二十時過ぎ。
空は茜色に染まっている。
緯度の高いエズミアでは、夕暮れが訪れるのも遅い。
黒紫塔の影がどこか遠くへと伸びている。
黒紫塔は、初めて間近で見た頃と何も変わらない。
ふもとの登山口には、許可証を持つ地元民と祭事関係者が列を作っていた。
係員が一人ずつ証を確認している。
ここからの昏渡りの儀式は、許可証を持つ者しか見ることができない。
許可証のことを知らず、登山口に入る気でいた観光客が係員に食い掛かっているのが見えた。
「もうすぐ夜になるってのに、今から山登るとかどうかしてるわ」
ぼやきながら、レイルは両腕を伸ばして背中を反らす。
これから山を登る前に一旦休憩が挟まれる。
黒紫塔のある広場までは、歩いて二十分。
それから三十分、最後の儀式が執り行われ、昏渡りは終わる。
最後の新成人がランタンを係員に返すと、休憩のアナウンスが響いた。
周りにいた新成人たちは、一斉に散っていく。
新成人の家族が駆け寄り、記念写真を撮り始める。
祝いの声をかけてもらい、照れくさそうにしている。
周囲を見回すと、母親にローブを直されている子が目に入った。
顔を真っ赤にして、恥ずかしそうに手を振り払おうとしている。
――もし、母さんが生きていたら……
一瞬、そんな想像が頭をよぎる。
だがすぐに首を横に振った。
考えても仕方のないことだ。
浮かびかけた思いを、強引にどこか遠くへと追いやった。
「じゃ、またあとでここ集合な」
スノアが顔の前で軽く片手を挙げた。
サニがひとつうなずくと、スノアたちは足早にそれぞれ家族のもとへ向かっていった。
***
辺りはごった返していた。
観光客に係員、出店の準備をしているスタッフまで、雑多な人波が渦を巻いている。
父と姉と合流しようと人混みの中を進むが、肩や腕が何度もぶつかりそうになり、足取りは思うように進まない。
立ち止まればすぐに押し流されてしまいそうだ。
道の脇では、いくつもの露店が軒を並べている。
香ばしい焼き串の匂いに、甘い果実酒の香り。
色とりどりの布が翻り、街灯の明かりが淡く揺れていた。
耳に飛び込むのは笛と太鼓の軽快なリズム。
広場の一角では楽団が演奏を響かせる。
その向かいでは奇抜な衣装のパフォーマーが宙返りを決め、拍手を浴びていた。
目を引いたのは、犬や鳥や馬の面をかぶった集団。
子どもたちが歓声を上げながら取り囲んでいる。
その後ろにはアニメキャラクターそっくりに着飾った若者や、まるで軍の特殊部隊員のような格好の男まで。
まるで街全体が演劇の舞台にでもなったようだ。
人混みの先、案内板の下で父と姉が並んで立っていた。
先に気づいたのは姉のフィアだった。
ぱっと手を振り、にこやかに笑う。
首元では、母の形見のペンダントが手を振るのに合わせて大きく揺れている。
少し遅れて顔を上げた父のアベルは、肩を落としてどこかくたびれた様子に見えた。
肩にはトートバックを下げている。
サニは駆け寄った。
「父さん、疲れてない?なんかあったの?」
フィアがくすくす笑って、父を横目で見た。
「お父さんね、ふもとの広場で待ってようって言ったのに、サニが歩いてる姿を見てたい、って聞かなくて。ずっと後を追ってたのよ?気づかなかった?」
サニは額を押さえた。
思い出すのは三年前、サニが十二歳の時。
姉フィアが十五歳となり、昏渡りに臨んだ日のことだ。
新成人が進む整然とした通路とは違い、見物人の通路は人であふれ返っていた。
肩が触れ合い、足を止めればすぐ後ろから押されるような雑踏の中を進む。
父は最初こそ張り切って先頭を歩いていたが、一時間も経つと足取りは重くなった。
大通りから外れて先に待ち合わせ場所へ行こう、とサニが提案しても、父は首を横に振り、頑として譲らない。
しまいには逆に、サニが父の手を引っ張って人波をかき分けながら、フィアを追いかける羽目になったのだった。
あれだけしんどい思いをしたのだから、今回は無理をしないと思っていた。
だが、予想は外れた。
我が子のこととなれば、多少の無茶でもやってしまうのが我が父なのだ。
サニは鼻先で小さく息を漏らした。
「もう無理すんなよ。帰って休めって。明日も仕事だろ?」
「何を言う!」
父は急に背筋を伸ばし、胸をぐっと張った。
「ここからが昏渡りの本番だろ!仕事に備えるために息子の晴れ姿を見ずに帰る父親がどこにいる!
仕事は三番目に大切なことだ。だから、仕事よりもサニを最後まで見ることが優先だ」
「一番と二番は何なんだよ……」
「そりゃフィアが一番、サニが二番に決まってるだろ」
父の大きな手がフィアの頭をぽん、と撫でる。
「……俺、二番なのかよ。そこは家族が一番とでも言ってくれよ」
「娘のほうがかわいい。世の父親にとっての常識だ」
サニは溜め息をついた。
フィアはわずかに口角を上げつつも、肩をすくめるようにして父を見返している。
フィアは亡くなった母に似てきた気がする。
***
サニが八歳の時、母ルミナが亡くなった。
それ以来、父は過保護気味になった。
母がいた時も家族は大切にする人ではあったが、少し頑張りすぎに感じることが多くなった。
通学は一人で十分な年になっても、父は毎朝トラムの停留所まで付いてきた。
風邪をひけば、寝室のドアをそっと開けてはハーブティーを淹れ直す。
気づけば隣の椅子でうたた寝をしていることもあった。
仕事で疲れていても、不慣れだった家事もこなしてくれた。
母の分まで、自分たちの成長に寄り添おうと必死になっているようだった。
そんな父をありがたいと思う気持ちは大きかった。
だがそれと同じくらい、いつか壊れてしまうんじゃないかという不安も膨らんだ。
その背中がどこか頼りなく、今にも折れてしまいそうに見える瞬間もあったからだ。
独りでいるとき、抜け殻のようになっていることもあった。
フィアは自然に家事を手伝うようになり、サニもそれを真似た。
父の負担を少しでも減らすために。
いつしか父が家事に追われることはなくなり、穏やかな顔を見せることが増えた。
***
フィアがサンドイッチを目の前に突き出してきた。
「ほら、食べとかないと、最後の油塗りの式まで持たないよ」
気づけば父は、立ったまま両手にサンドイッチを握り、もう頬張っていた。
疲れを誤魔化すかのように、やけに勢いよく。
その様子に呆れつつ、サニもハムとチーズの挟まったものを手に取る。
「サニは、最後の式で何を誓うんだ?」
もごもごと咀嚼しながら、父が聞いてきた。
「やっぱり母さんと同じで、黒紫塔を調べるって誓うつもりか?」
「そうだよ」
サニはかぶりつく。
鼻先にケチャップとマスタードのつんとした匂い。
マスタードを厚く塗るのが、我が家流だ。
父はじっとサニを見つめ、やがて視線を落とす。
何か言葉を探すとき、決まってそうするのが父の癖だ。
父の様子を見ていたフィアが、言いにくそうにサニの顔をのぞき込んだ。
「……サニ。無理して母さんと同じことをしなくてもいいんだよ?」
サニの眉がぴくりと動く。
「やめろって言いたいのか?」
「そんなこと言ってないでしょ。ただ……あんたが母さんのやり残したことを、無理して引き継ごうとしてるんじゃないかって思って……」
サニはむっと顔をしかめた。
「無理に継ごうとなんてしてない。俺は自分のやりたいことをやろうとしてる。それに、何をやるかなんて俺の自由だろ」
吐き捨てるように続ける。
「それとも、姉ちゃんは俺に“もっと現実的な夢”を考えろ、って言いたいのか?」
フィアは言葉を探すように視線を泳がせた。
「そういうことじゃなくて、私が言いたいのは――」
フィアが言いかけたところで、父が片手を上げて制した。
父は口の中のものを飲み込むと、すぐにもうひと口かぶりつく。
「サニ」
「何だよ?」
父は目を閉じ、サンドイッチをゆっくり咀嚼した。
「サニが本気なのは、父さんもフィアもわかってる。もう十五だしな。将来のことも考える歳だ」
父は飲み下すと、まっすぐに視線をこちらへ向けた。
「昏渡りで何を誓うかは自由だ。誓ったからって絶対にやらなきゃいけないものでもない。形だけのことだと言えば、それまでだ」
「なら、別に母さんと同じこと誓ったっていいだろ」
父がフィアをちらりと見る。
フィアは容器を握りしめ、黙って父を見返していた。
「フィアが心配してるのはな、サニが母さんの夢に縛られてるんじゃないかってことだ」
「縛られてなんかない!」
サニの声がやや強く跳ね返る。
だが父の表情は揺れなかった。
「母さんと同じ道を選ぶのはいいことだ。きっと母さんも喜ぶ。
でも……もし本当にやりたいことが別にあるなら、それを選んでもいい。無理して母さんに合わせなくてもいいんだぞ?」
「だから無理してないって!」
サニはサンドイッチを乱暴にかじり、無理やり飲み込む。
父はゆっくりと息をはいた。
「黒紫塔を調べても、何に役立つかはまだ誰にもわからない。世間じゃただの観光物程度にしか思われてない。
だから、そういうものに入れ込むことを無駄だと笑うやつは必ずいる。役に立たないと決めつけて、好き勝手に口を挟んでくる。……世の中、そういうもんだ」
「じゃあ俺も、その“そういうもん”に合わせて、母さんと同じ夢を追うのはやめろって言うのか?
昏渡りって節目に、周りから褒められる夢でも探せって?」
語気が荒くなる。
「違う」
父は鼻で笑い、口角を上げる。
「逆だ。周りが何を言おうと、簡単に夢を諦めるな。フィアも父さんもそれが言いたいんだ」
サニは瞬きをした。
「サニ。夢ってのは、このサンドイッチみたいなもんだ」
父はマスタードが垂れそうなサンドイッチの断面を見せつけてきた。
また変なことを言い出した、とサニは白い目を向けた。
「中に何を挟むかは自分で決める。ハムでもチーズでも、好きな具を選べばいい。人それぞれ好きなサンドイッチが作れるんだ。誰かに決められるものじゃない」
「それ、中に何挟むか決めたのは、姉ちゃんだろ……」
「でも、どれを食べるか選んだのは、父さんだ」
父は残りのサンドイッチを口の中に放り込んだ。
「サニが母さんに縛られていないのは、よくわかった。
でも、周りはなんでも好き勝手に言う。本人がどれだけ努力して、本気でいても関係ない。それぞれの“常識”って物差しで測り、それを押し付けようとしてくる者もいる。
だから、夢を貫くには、ただ“やりたい”って思うだけじゃ、その“常識”に負けて、心が折れてしまうこともあるんだよ」
「……じゃあ、どうすりゃいいんだよ」
父は得意げな顔をして、胸を張った。
「選んだ自分を信じろ!」
真剣な目がサニを射抜く。
「夢の価値を決めるのは周りじゃない。決めるのは――サニ、お前自身だ。
周りはな、『そのサンドイッチの具は抜け』『それはやめて人気のにしとけ』って、好き勝手に口を出してくる。自分で食べるわけでもないくせにな。
けど、誰かの言うとおりに変えてしまったら、それはもうサニの好きなサンドイッチじゃなくなる。食べたときに本当に“うまい”って思えるのは、自分で選んだものだけだ。夢も同じさ」
父の声はいつになく真剣で、まっすぐに響いてきた。
サニはその瞳を真正面から受け止める。
自分で選んだもの。
その言葉が胸の奥で反響する。
気づくと、六歳の頃に初めて黒紫塔を見上げた記憶がよみがえってきた。
母になぜ黒紫塔を調べてるのか尋ねたときのことを思い出す。
***
あのとき母は、やわらかく微笑んで――
「楽しいからかな」
そう答えた。
けれど、幼い自分には、黒紫塔をじっと眺めるのが楽しいとは、とても思えなかった。
「でも、これ見てるより、木に登ったりして遊んでるほうが楽しいよ?」
無邪気に言い返した自分に、母は目を細めて笑った。
「それは、サニが楽しいことでしょ」
くすくすと笑いながら、母は草むらにちょこんと座る自分の目線に合わせて、ゆっくりと腰を下ろした。
「じゃあもし――」
母は少し首をかしげて、悪戯っぽく白い歯をのぞかせる。
「お母さんがサニに『黒紫塔を見てるほうが楽しいんだよ。だから木登りなんてやめて、こっちに来なさい』って言って、サニに同じことをやらせたら……サニは楽しいって思える?」
サニはぷるぷると首を横に振った。
「でしょ?」
母はにっこり笑って、サニの鼻先を指で軽くつついた。
「サニが木に登るのを楽しいって思うように、お母さんは黒紫塔をこうやって見てるのが楽しいの。
人から押しつけられたことじゃ、楽しいって感じられないんだよ。
楽しいと思えるのは、自分で選んだものなんだよ。それはお母さんもサニも同じ」
「ふーん……」
気の抜けた返事しか出てこなかった。
幼い自分にとって、“楽しい”は自分だけのもので、他の誰かの“楽しい”ということが想像もつかなかった。
そのことを母は察したのだろうか。
それ以上は何も言わず、ただ草むらに座るサニの頭をやさしく撫でてくれた。
***
黒紫塔を研究して何になるかは、確かにわからない。
近所の連中は熱心に黒紫塔を調べる母を変わり者と呼び、馬鹿にする声もあった。
新興宗教にでものめり込んでる、という噂まで広がっていたらしい。
それでも母は迷わなかった。
周りの言葉に振り回されず、自分の決めた道を歩き、いつも笑っていた。
「どんな言葉を投げられても気にするな。笑われたら、笑顔を返せ。
自分が選んだものを信じられるなら、どんな常識も跳ねのけられるさ。母さんはそうやって生きてた」
父の手がサニの背をばしっと叩く。
思わず体が揺れる。
「母さんと同じ道を歩くってんなら、その生き方も継げ。そして、その生き方を選んだ自分を信じろ」
サニは父の目を見て、大きく、力強くうなずいた。
「父さん……姉ちゃんも、ありがとう」
フィアは胸を撫でおろし、父は満足げに決め顔を浮かべた。
――が、すぐに父の表情が固まると、「あっ」と声を漏らした。
背中を叩いた手には、マスタードがべったり。
サニの背中には、黄色い手形がくっきりと残っていた。
フィアが慌ててハンカチを取り出し、サニの背を拭く。
父は「い、いや、これは……」としどろもどろになり、せっかくの決め顔も台無しになった。
ごしごしと背中を拭かれる感触に、サニは思わず笑みをこぼした。
胸の奥に、父の言葉が静かに根を下ろしていくのを確かに感じた。
そのとき、ふとサニの目の端で、黒い塊がふわりと揺れた。
建物の陰に何かが浮かんでいる。
目を凝らすと、それは全身を長く黒い毛に覆われた、見たこともない生き物だった。